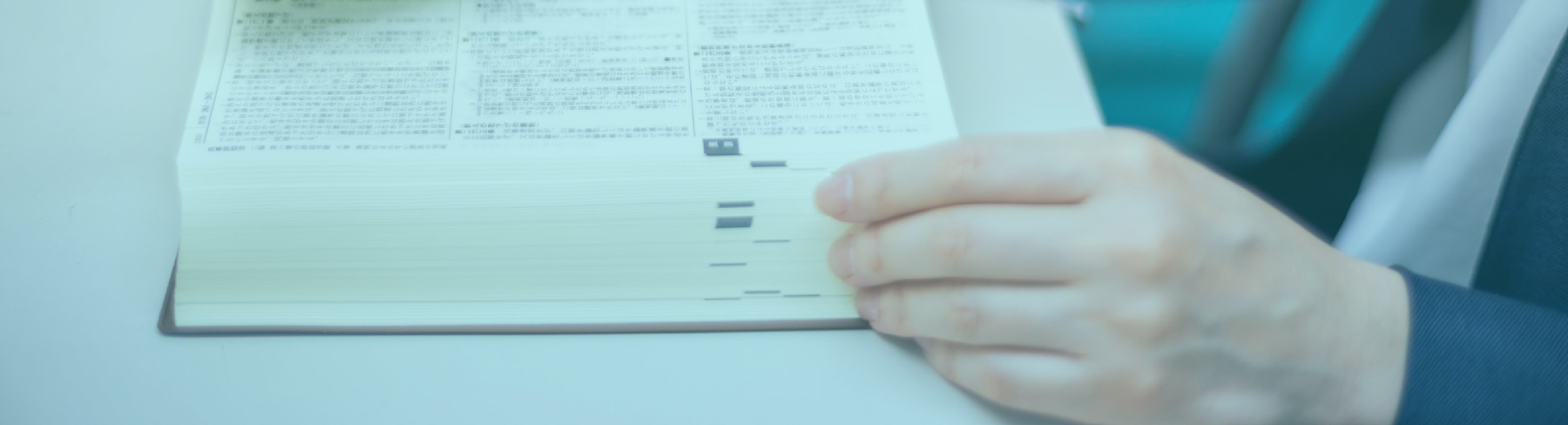その他
2025.02.13
三子教訓状
「多くの矢をひとつにして折たらんには細き物も折がたし―」
毛利元就が、自身の三人の子(毛利隆元、吉川春元、小早川隆景)の前で、三本の矢をひとつに束ね、これを一度に折ることが難しい様を見せ、兄弟の結束が何より重要であると説いたとされる「三本の矢」の話は皆さんもよくご存じかと思います。
この話の元ネタとされるものとして、「三子教訓状」があります。これは、毛利家が防長経略を終えた頃、三人の息子に対して宛てた、協力して毛利家を繁栄させるよう14カ条に渡って諭す手紙です。書状の長さは約3Mに及び、内容もあまりに濃いためここでは割愛しますが、主には他家の家督を継いだ春元、隆景と、毛利家の家督を継いだ隆元の協力関係を説くことで、隆元の主君としての地位を強固にし、毛利家内の内紛を防止し、いわゆる「毛利両川体制」と呼ばれる統治体制を確立するための教示であったのではないかと考えられているようです。
考え方や立場の違う者同士では、一つ謀があればその関係が瓦解してしまうことを、謀略を駆使してきた元就は誰より熟知していたはずであり、だからこそ身内・家臣の強固な関係・団結を何より重視し周囲に説いてきたのでしょう。
話は変わりますが、こと労使間の紛争においても、労働者側はなかなか一致団結というわけにはいきません。労働者は基本的に使用者の指揮監督下にあり、使用者から賃金を支払われることによって生計を立てざるを得ないわけですから、たとえ労働者の一人が使用者から不当な扱いを受けたと声を挙げても、他の労働者は使用者の利益に反してまでその労働者の味方をすることが難しいというわけです。
労働者間もそれぞれ立場や考え方は違うと思いますが、それでも互いの利害を超えて協力・団結していかなければ、労働者にとっての正当な権利の主張というのは難しいと感じさせられます。